いつまでも元気に旅しよう!病に勝つカラダ 第12回
いつまでも若々しく元気に活動したいし、旅行にも出かけたい。
そのために病気にならないカラダ作りを予防医学の観点から毎号お届けします。
睡眠中に行われている、脳の掃除と体のメンテナンス。
私たちは眠ることで、心身にたまった疲れをリセットし、脳を活性化しています。
最近、睡眠不足が認知症のリスクを高めることがわかり、再認識される睡眠の重要性。
よりよい睡眠を得るための「眠活法」をご紹介します。
短時間睡眠で認知症のリスクが高まる!アメリカのジョンズ・ホプキンス大学の研究グループが、2013年に発表した論文によると、睡眠時間が短いと、認知症の原因物質であるアミロイドβが、神経細胞に蓄積しやすいことがわかりました。
研究では平均年齢76歳で認知症を発症していない被験者70名を調査して、睡眠時間とアミロイドβの蓄積量を比較しています。すると、睡眠時間が6時間未満のグループは、明らかにアミロイドβの蓄積量が多かったのです。
これにはちゃんと理由があります。私たちが体内で生命活動を行っているとき、ゴミのようなものが生じます。このゴミの排泄がスムーズにできず、細胞内にたまっていくと、病気や老化が促されてしまうのです。
脳でも毎日ゴミが発生しているのですが、実は、眠っている間にこのゴミが洗い流されていたのです。
そのため、睡眠時間が短いとゴミの排泄が十分にできず、認知症のリスクが高まることが明らかになりました。
脳だけではありません。私たちは眠っている間に、全身の傷ついた細胞を修復して、脳はもちろん全身のメンテナンスを行っているのです。
ところが、日本人の睡眠時間はどんどん短くなっています。厚生労働省の「国民栄養・健康調査」によると、睡眠時間が6時間未満の人の割合は、平成20年の29・7%から、平成27年は39・5%へと増加。逆に7時間以上の睡眠をとっている人は34・5%から26・5%と大幅に減っています。残念ながら日本人は世界でもトップクラスの睡眠不足のようです。「短時間睡眠」を勧める人もいますが、睡眠に大事なのは「時間」と「質」の両方です。脳と体の疲れをとるためには、ダラダラと長時間寝るのも良くないですし、熟睡できれば短時間睡眠でよいということでもありません。
ただ、私たちに備わっている睡眠をコントロールするシステムは、加齢とともに低下してしまいます。齢を重ねるほど眠りについての悩みを抱える人が増えてきます。また、前立腺肥大でトイレが近い、糖尿病でのどが渇きやすいなど、持病の影響で眠りに弊害が出るケースも少なくありません。
よりよい眠りを得るためにどうすればいいのか、青山・表参道睡眠ストレスクリニックの中村真樹先生がすすめる「眠活法」を紹介します。
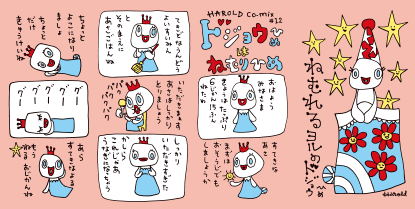
メラトニン分泌を妨げず
睡眠リズムを整えるよりよい睡眠をとるために日中の生活で気をつけることを「眠活法」として提唱している中村先生によると、熟睡できるかどうかは睡眠のリズムをコントロールしているメラトニンというホルモンがカギとなります。メラトニンの分泌量が多いと眠気を感じ、分泌量が減ると眠気が軽くなります。
メラトニンは朝起きて強い光を浴びると合成・分泌がストップし、目覚めてから14〜16時間ほど経過すると再び分泌量が増え始めます。例えば朝6時に起きると夜8〜10時くらいからメラトニンの分泌量が増え、しばらくすると眠気が生じることになります。
夕方以降に強い光を浴びるとメラトニンの合成が弱まってしまいます。睡眠リズムを保つためには、朝起きたら午前中は明るい日差しのある場所で過ごし、夕方以降はメラトニンの分泌を妨げるブルーライトを避けるため、室内照明を電球色にし、パソコンやスマホの画面など液晶ディスプレイを見続けることをなるべく避けるようにしましょう。
年代によっておすすめの「眠活法」が違いますが、ノジュール読者世代は昼寝とコーヒーを飲む時間に注意しましょう。
退職後、時間があるからと昼に長時間の昼寝をしていると、起きているときに増える睡眠物質が減ってしまうため、夜に眠気が起こりにくくなります。昼寝は「午後3時までに30分以内」と決めて、計画的に行いましょう。
また、コーヒーなどに含まれるカフェインにはこの睡眠物質の一つであるアデノシンをブロックする働きがあります。カフェインの効果は3〜4時間続くので、コーヒーや紅茶、お茶などカフェインを含むドリンクは夕方4時頃までに飲むようにしましょう。
高齢者では実際には眠れていても、加齢による中途覚醒や早朝覚醒を理由に「不眠」を心配するケースがあります。朝起きたときにすっきりと目覚め、日中に強い眠気が起きないようであれば、睡眠は十分に足りています。あまり気にしすぎないようにしましょう。
なかむら まさき●青山・表参道睡眠ストレスクリニック院長。
日本睡眠学会認定医。東北大学医学部卒業後、同大学附属病院精神科助教・外来医長、睡眠総合ケアクリニック代々木院長などを経て現職。
臨床と研究の両方から睡眠の問題に取り組む。著書に『仕事が冴える眠活法』(三笠書房)。
https://omotesando-sleep.com

