「新時代医療(ネオメディカル)」のススメ 第9回
日々進歩する予防医学。
新元号となる2019年は、“未病”対策を見直してみませんか?
新時代の健康なカラダ作りのために知っておきたい、医療業界の最新トピックスを毎号お届けします。
超高齢社会を迎えた日本では、病院が遠い、交通手段がないなど、通院が困難な人の増加が指摘されています。
また、難病の療養や慢性疾患などの場合は、患者さん本人が「自宅で過ごしたい」と希望するケースも増えてきています。
医師が自宅での療養が可能と判断したときに、選択肢のひとつとなるのが「在宅医療」です。
「在宅医療」とは自宅などで受ける医療のこと。
今月は、長年、在宅医療に取り組む永井康徳先生にお話を伺いました。
超高齢社会の到来が病院不足、通院困難を生む超高齢社会を迎えた日本では、今後療養が必要な高齢者が確実に増加します。この増加に対して、受け入れる医療施設が十分とはいえません。特に人口の多い都市部では入院する病院や施設が不足し、行き場を失う患者さんが増えると懸念されているのです。
また、超高齢社会のその先、団塊の世代が80代後半を迎える2030年以降、日本はこれまでに経験したことのない多くの死を迎える「多死社会」が到来します。
いまの日本では8割近くが病院で死を迎えています。医療費の増大が懸念されていますが、もっと切実なのはベッド数の不足といえます。
それらを解決するために厚生労働省がすすめている施策のひとつが、在宅医療の推進。在宅医療とは、広い意味では病院外で行われるすべての医療のことで、医師が自宅などでの療養が必要だと判断したときに受けられるサービスです。
在宅医療では医師だけでなく、看護師、理学療法士、管理栄養士、薬剤師といった医療者が自宅を訪問し、医師の指示のもと連携して患者さんをサポートします。歯科医師や歯科衛生士が行う「訪問歯科診療」もあります。
具体的には、医師が自宅を定期的・不定期に往診・診療します。必要があれば看護師が訪問して処置や世話を行いますし、薬剤師や管理栄養士が訪問して薬の飲み方や食事や栄養状態の指導を行うこともあります。理学療法士や作業療法士は日常動作がスムーズに行えるようリハビリテーションを行ったり、過ごしやすいよう家屋の改造をアドバイスしたりします。
在宅医療がこれまでの医療と異なる のは、医療者が患者さんと同じ立場に 立って、いっしょに考えながら歩む、 “支える(サポートする)医療”である ことでしょう。
高齢化が進んだ日本ではこれまでの 「病院での治す医療」だけでは解決で きない問題も出てきています。
国は「治せなくても支える医療」への転換を図ろうとしており、その中心となるのが在宅医療なのです。
さらに、在宅医療は「死に向き合う医療」でもあります。
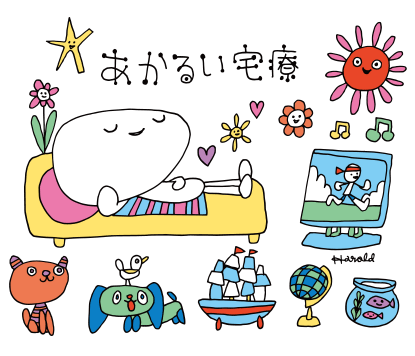
いつか必ずくるその時を
どう過ごすか考える在宅医療では、ゆくゆくは必ず迎える看取りについて、患者さんや家族といっしょに考えます。生きているかぎり、いつかは必ず迎える死。死が近づいたとき、死を感じたときに「どう生きるか」について語り合うのです。
在宅医療で「死」について考えることが重要なのは、終末期の医療では患者さん自身の人生の価値観や希望で、どのような医療ケアを受けるかが変わってくるからです。
いまの日本の医療現場には「死は医療の敗北である」という風潮があります。最後まで治し続けようとする医療者や、少しでも長く生きて欲しいと願う患者さんの家族が多数を占めているのです。
もちろん、最後まで治し続けようとすることも選択肢のひとつです。しかし、永井先生の経験では、ある程度の年齢になると、「もう十分生きたし、最後は楽に過ごしたい」と思う人も少なからずいらっしゃるそうです。
有効な治療手段がないこと、限られた命であることを伝えることを予後告知と言います。これは命の期限を伝えることではありません。あくまでも大まかな目安です。ただ、それを知ることで、その後の生き方がまったく違ってくると永井先生はいいます。死に向き合うことで初めて考えられることがあり、生き方が変わるのだそうです。
死について考え始めるのは早ければ早いほうがいいとのこと。また、決めなくてもいいのです。家族や周囲の人と話したり、考えたりするプロセスが大事なのだそうです。
厚生労働省は人生の最終段階における医療やケアについて、患者さん本人がどう望むのかを前もって考え、周囲の信頼する人たちと話し合い、共有する取り組み「アドバンス・ケア・プランニング(ACP)」をすすめています。
昨年、公募のうえ「人生会議」という名称やロゴマークが決まり、11月30日(いいみとり)は「人生会議の日」となりました。この日はむずかしくなく、いつか迎える「死」について誰かと話してみてはいかがでしょうか。
永井康徳 〈ながい・やすのり〉
医療法人 ゆうの森、理事長。
1992年、愛媛大学医学部卒業後、同大学医学部附属病院、自治医科大学地域医療学教室などを経て、2000年に在宅医療専門診療所「たんぽぽクリニック」を開業。
僻地診療所、訪問看護ステーション、訪問介護事業所などの運営を手がける傍ら、在宅医療従事者の教育に積極的に取り組む。
tampopo-clinic.com
