東西高低差を歩く関西編 第29回
地形に着目すれば、土地の歴史が見えてくる。
“高低差”の達人が紐解く、知られざる町のストーリー。
関東は皆川典久さん、関西は梅林秀行さんが交互にご案内します。
~断層崖と海食崖が生んだ、大阪の緑と坂道~
上町台地
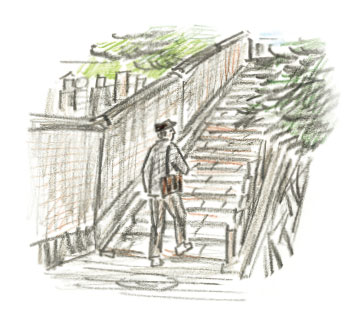
イラスト:牧野伊三夫
大阪平野に横たわる上町〈うえまち〉台地は、南北約11㎞、東西約2〜3㎞の細長い形をしている。この台地の位置は市街地中心部だけあって大阪人にとってはおなじみの反面、他府県人にはややなじみ薄いかもしれない。地形の知名度ではローカルスターといったところだろうか。
巨視的に見れば、上町台地は日本列島を東西から圧縮するダイナミックな地殻変動によって誕生した。現在に至る地殻変動は、海洋プレートと大陸プレートの関係変化に応じて約100万年前から活発化しているが、これを地学では六甲山を示標にして「六甲変動」と呼んでいる。大阪平野や京都盆地、奈良盆地などの平野・盆地部、そして六甲山地や生駒山地、京都の東山などの山地部と並んで、大阪の上町台地も六甲変動という地殻変動で生まれた地形なのである。
さらに上町台地の特徴をクローズアップすると、この台地は六甲山地―淡路島―和泉山脈によって形づくられる、環状の沈降域の東縁ラインと見ることもできるかもしれない。北東―南西方向に軸を向けた楕円形の凹地に海水が浸入したものが大阪湾であり、上町台地はこのうち東側の「へり」に相当するものと理解してよいだろう。ひとつの地形は、周辺の環境に視野を広げると把握しやすい。上町台地もその例に漏れないということだ。
このような地殻変動によって生まれた上町台地は、台地の上下で現状約15mもの比高差、地面のズレを生みながら隆起を続けてきた。すなわち断層運動である。上町台地では、西側に併走する上町断層が台地を隆起させた直接的な原因と考えられている。
しかし、上町台地の特徴は断層運動にとどまらない。この台地の興味深い点は、上町断層を生んだ地殻変動が台地を隆起させた後、大阪湾の海水浸食作用によって「断層崖」が「海食崖〈かいしょくがい〉」に性格変化したというところにある。その時期は縄文時代早期(約8000年前)。急激な気温上昇によって極地の氷が溶けたことで地球規模の海面上昇が起きた、いわゆる「縄文海進」と呼ばれる現象である。これによって海面が現在に比べて2〜3m上昇し、日本列島各地で海水が奥地まで侵入することになった。
縄文海進によって拡大した海面は現代の大阪平野一帯に広がり、すでに隆起していた上町台地は海に浮かぶ島、あるいは半島のように当時は見えたことだろう。この際、もともと上町台地を形づくっていたはずの上町断層の断層崖は、押し寄せる海の波に削り取られ、台地西側の崖は約300m以上も位置が後退することになった。現在、上町台地東縁の崖は直線的なラインで南北に連なっているが、それがまさしく縄文海進が生んだ海食崖そのものである。この風景を特徴的と言わずしてなんと言おうか。
今も大阪市中央区から天王寺区にかけては、上町台地の東縁斜面が大型ビルの建ち並ぶなかに緑地帯として続いている。
梅林秀行 〈うめばやし ひでゆき〉
京都高低差崖会崖長。京都ノートルダム女子大学非常勤講師。
高低差をはじめ、まちなみや人びとの集合離散など、さまざまな視点からランドスケープを読み解く。「まちが居場所に」をモットーに、歩いていきたいと考えている。
NHKのテレビ番組『ブラタモリ』では節目の回をはじめ、関西を舞台にした回に多く出演。著書に『京都の凸凹を歩く』など。

