東西高低差を歩く関東編 第53回
地形に着目すれば、土地の歴史が見えてくる。
“高低差”の達人が紐解く、知られざる町のストーリー。
関東は皆川典久さん、関西は梅林秀行さんが交互にご案内します。
京都・北野
平安京北方に生まれた
聖地の理由
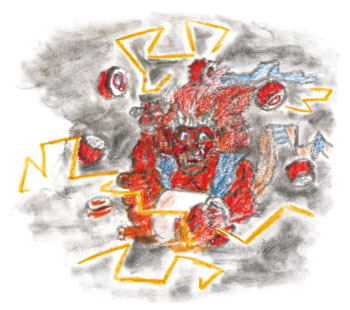
イラスト:牧野伊三夫
東西南北の方角は多くの文化・文明にとって、単なる位置情報ではない意味をもっていた。とりわけ東アジア世界ではそれが顕著で、たとえば仏教では西方に「阿弥陀浄土」があるとされたように、各方角には特別な意味があった。
このような意味付けのなかで、とりわけ重視された方角は北である。古代中華王朝が皇帝と臣下の関係を、天空の不動の定点である北極星とそれを周回する星々に見立てたことによって、北は単なる方角ではなく世界の秩序に関わる至上の地位を占めることになった。
結果、皇帝・王が君臨する都でも北は至上の方角と理解されて、古代日本の都もその影響を受けてか、奈良時代以降、平城宮や平安宮などの王宮は都の北辺に位置し、王宮のさらに北方の郊外は中華王朝と同様に「禁苑〈きんえん〉」(天皇専用の土地)として、祭祀〈さいし〉や遊興〈ゆうきょう〉に使用されていた。
京都盆地は鴨川などの北から南へ流れる河川によって、扇状地が分厚く発達している。京都の地点表記として有名な「上〈あが〉ル」「下〈さが〉ル」も、扇状地の堆積状況が北から南へ傾斜する土地柄ならではの言い回しだろう。すなわち、平安京は地形環境として「北高南低」の条件が用意されており、北極星の至上の地位はそのまま扇状地の地形高低にも反映されているのだ。
このような特別な方角・地形が平安京の北方には意味付けられており、その土地を古代の天皇や貴族たちは、特別な意味を込めてか、北野と呼ぶようになった。現代の京都で「天神さん」と親しまれる北野天満宮は、平安京の北方に設定された特別な土地に鎮座しているのだ。
そもそも北野天満宮は、その名のとおりに北野に位置しており、明治維新以前は比叡山末寺としての性格を備えた、「宮寺〈みやでら〉」とも呼ばれる神社と寺院の性格を合わせもつ聖地だった。祭神はご存知のとおり、平安時代前期末の学者・政治家だった菅原道真である。藤原氏以外の氏族出身として異例の栄達を遂げる一方、そのために起きた権力闘争の敗者となって平安京から九州に流罪、その地で寂しく最期を迎えたものの、後に怨霊として天皇や貴族たちを恐怖の底に突き落とした物語はよく知られている。
このような道真だが、死後どのように北野へと鎮座するようになったのか。鎌倉時代中期の弘安元年(1278)頃に成立した『北野天神縁起』によれば、死後道真は平安京の庶民女性だった多治比文子〈たじひのあやこ〉に託宣を下し、そのなかでみずからを祀る聖地造営を命じている。託宣の内容を現代語訳してみよう。「生前の私は北野にある右近馬場〈うこんのばば〉まで毎年遊びに行っており、そこは都の周辺でも景勝地としてひときわ優れていた。しかし無実の罪で流刑となり、都からはるかに離れた九州で客死したといえども、霊となって密かに右近馬場を訪ねて遊ぶ時のみ、心の炎が少し消える気持ちがする。ぜひそこに私を祀りなさい」
このとき道真が、怒りと嘆きの心理状態を「心の炎」(縁起原文でも「心のほのをすこし消ゆる心地する」と表記)と現代人にも通じる言葉で表現したことも面白いが、それに加えて右近馬場という場所を特別扱いしていることがさらに興味深い。
右近馬場とは、本来は天皇を守備した右近衛府〈うこんえふ〉の馬場のことだが、所在地が天皇の「禁苑」である北野の一部だったこともあり、後に天皇が貴族を連れて行幸し、狩りや宴会を楽しむ遊興の場所に性格を変えていった。道真も天皇行幸に随行して、存分に北野の右近馬場を楽しんだのだろうか。内裏に雷を落とすなど、最強の怨霊として強烈な怒りと深い嘆きを抱えた道真も、右近馬場での遊興に象徴される栄達の記憶によって魂が慰められたにちがいない。思わずそこに、リストラやレイオフなど、現代人の悲哀に近いものを感じてしまう。
今、北野天満宮を訪れると、正面参道が大きくカーブする箇所がある。これは平安京からまっすぐ北方へ伸びる天満宮の参道が、途中で右近馬場を避けて迂回した結果である。これは道真の託宣どおりに、北野天満宮が右近馬場のすぐ隣に設置された証であり、平安京北方の特別な意味、そして道真の「心の炎」を今も感じられる風景なのだ。
梅林秀行 〈うめばやし ひでゆき〉
京都高低差崖会崖長。京都ノートルダム女子大学非常勤講師。
高低差をはじめ、まちなみや人びとの集合離散など、さまざまな視点からランドスケープを読み解く。「まちが居場所に」をモットーに、歩いていきたいと考えている。
NHKのテレビ番組『ブラタモリ』では節目の回をはじめ、関西を舞台にした回に多く出演。著書に『京都の凸凹を歩く』など。

