[エッセイ]旅の記憶 vol.34
旅、旅、旅
吉村 作治
私の旅好きは父親譲りです。ただ父親の旅は写真集や地図、旅のエッセイを読み、目から入った情報を脳で楽しむ“目”の旅です。今では衛星放送などで世界中の旅が紹介され、父が生きていたらさぞかし毎日が楽しく過ごせただろうと思います。
私の旅は実践派です。中学受験に成功した記念に九州一周をしました。当時から歴史や時事問題に興味があり、長崎の原爆資料館を訪れたり、種子島の鉄砲伝来の地へ行ったりしました。東京駅に着いた時、ポケットに25円しか残っておらず、タクシーで帰宅し、母に料金を払ってもらったことを思い出します。
その後、中学と高校を通して休みは全て旅にあて、日本全国をまわりました。旅が私を育ててくれたと言えます。旅というより、旅で出会った人々です。その究極が大学時代のある旅でした。小学校4年の時、いじめられっ子だった私はいつも1人で通っていた図書室で『ツタンカーメン発掘記』に出会い、考古学者ハワード・カーターに憧れ、将来エジプトに行って発掘するのを夢見ていました。そこで大学生になった私はその予行演習として初めての外国、沖縄・台湾に出かけたのです。当時、沖縄は米国支配下で右側通行、ドル払い、タックスフリー、基地と、知識はあっても、それを実際に体験するのはすごい事でした。台湾は大陸から逃げてきた人と原住の人との格差が大きく、それでも文化財を守ろうとする人々の心意気が熱く伝わってきました。
そして1966年9月、タンカーでエジプトに行き、7ヵ月半かけてナイル流域を踏査しました。全てが強烈な印象で食べ物も言語も住むことも何とかクリアできましたが、イスラム教だけはどうしてもわかりませんでした。私はこの調査旅行を終えて、一生をエジプト考古学にかけようと決め、ついにはイスラム教徒になりました。そしてイスラム教徒の悲願でもあるサウジアラビアのメッカ巡礼(ハッジ)をしたのです。この体験を通して私はユダヤ教、キリスト教をも学び、この3つの宗教は根源的には同じで、そのもとは古代エジプトの宗教だと知りました。そしてそれは私のエジプト考古学研究に深くて大きな影響を与えてくれたのです。
還暦になるまでは、ほとんどが仕事としての旅でした。国内は地方講演か旅番組のリポートですし、海外はテレビ番組の取材です。エジプトにいた20代はアシスタントでしたが、30代半ばからはディレクターとしてドキュメンタリー番組を作るようになりました。中でも一番印象に残っているのはNHKの「祈りのある生活」で、私自らカメラをまわして、イスラム教徒でなければ入れないメッカ巡礼の番組を作りました。最近は海外にプライベートで行く機会も増え、若い時、仕事でまわった跡を訪ねています。12歳から始まった私の旅は、地球上のほとんどの国々を網羅し、航空会社のフライトマイルの合算は300万マイルを超えています。人生って、生まれてから死ぬまでの長い旅だというのが私の感想です。
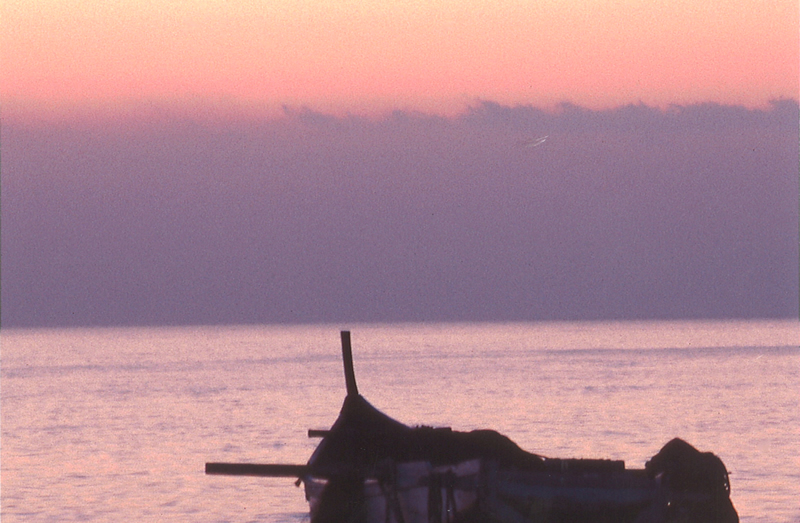
写真:大川裕弘
よしむら さくじ●1943年東京都生まれ。エジプト考古学者。
東日本国際大学学長。早稲田大学名誉教授。
1966年にアジア初のエジプト調査隊を組織し現地へ赴いて以来、
約50年にわたり発掘調査を継続。数々の発見により国際的評価を得る。
「日本の祭」を原点にした地域振興・創生の試み、
eラーニングを活用した教育の普及にも努めている。
著書に『人間の目利き』『エジプトに夢を掘る』、『教授のお仕事』など。
公式HPエジプトピアhttp://www.egypt.co.jp/

