東西高低差を歩く関東編 第14回
地形に着目すれば、町の知られざるすがたや物語が見えてくる。
「築かれた地」に建立された、東京のランドマークでもある
築地本願寺には、東京らしいエピソードがあった。
築いた土地
築地本願寺
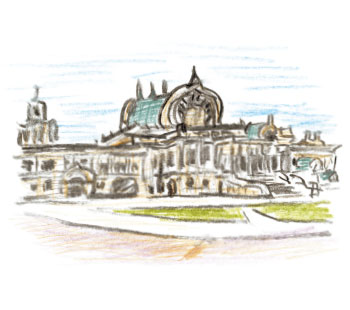
イラスト:牧野伊三夫
前回「東西高低差を歩く」は京都の東本願寺であったが、東京にも東本願寺があり、さらに西本願寺だってちゃんと存在する。都民なら誰もが知るあの寺院が西本願寺だ。まずは東本願寺について。東京の東本願寺があるのは台東区西浅草。浄土真宗東本願寺派の本山で、かつては東京本願寺と称していたが、昭和56年に起きた内紛を契機に京都の東本願寺より独立し、現在は「東本願寺」が正式名称となった。京都の東本願寺の正式名称は真宗本廟となる。開創は安土桃山時代の天正19年(1591)で、京都東本願寺の教如が神田に開いた江戸御坊光端寺がはじまり。江戸時代の初期に神田明神下へと移転したが、明暦3年(1657)の大火、通称「振袖火事」の後に現在の地に移転した。
振袖火事では10万人以上の死者が出たとされるが、当時の江戸の人口は35万人程度。それ以降江戸の町は防火対策として、延焼を防ぐ火除地〈ひよけち〉を設け、都心の寺院を郊外へと移転させる政策を取る。幕府が東本願寺に対し移転の地として指定したのは「千束池」と称された湿地が広がる土地。地形的には隅田川の後背湿地にあたり、出水の多い軟弱地盤で開発の遅れた一帯だった。ちなみに後背湿地と隅田川の間には帯状の微高地が存在し、その比較的安定した土地で発展したのが湊町・浅草だ。
続いて東京の西本願寺について。東京の西本願寺とは築地本願寺のことで、東本願寺と同じく振袖火事の後に移転させられたもの。幕府から与えられた代替地は葦〈あし〉が生い茂る浅瀬で、佃島門徒による埋め立てでできた「築かれた地」に建立したのが築地本願寺である。築地本願寺の正式名称は浄土真宗本願寺派本願寺築地別院で、本山が京都の龍谷山本願寺(西本願寺)だ。
築地と言えば豊洲へと移転した魚市場のあった町としてなじみ深いが、一帯は築地本願寺のために築かれた土地であり、築地場外市場があったのは元々築地本願寺の境内だった。そして築地本願寺と言えば、日本に数多ある寺院建築とは一線を画した独特なスタイルが話題にのぼる。あの建物は、関東大震災で消失した寺院を再建したもので、設計者は伊東忠太。東京駅の設計者として知られる建築家・辰野金吾に師事し、東京帝国大学で建築史を教える教授も務めた。
独特な意匠を持つ寺院の誕生には、発注者である築地本願寺の宗主・鏡如〈きょうにょ〉上人(大谷光瑞〈おおたにこうずい〉)と伊東の邂逅があった。大谷は仏教の源流をたどる大谷探検隊を結成。探検隊はシルクロードを西へと進み、天竺〈てんじく〉(インド)への旅路の途中で伊東と出会う。伊東は仏教建築のルーツを探す三年間にも及ぶ長い旅の途中であった。源流を探る壮大な旅を敢行した二人の出会いが、インド様式とも称される築地本願寺のデザインへと結実する。伊東によれば日本の仏教建築は中国や朝鮮半島を経由するうちに、仏教発祥の地インドの寺院から変容したものだという。だから仏教のオリジナル建築様式の追求が伊東の設計テーマであり、妄想の結晶として、あのユニークな建築が生まれたわけだ。
さて、源流探索とは二人の旅が象徴するよう遠く異国の地を彷徨うイメージがつきまとうが、都心を流れるの川の源流探索なら、半日もあれば可能である。その源流こそ自分が魅了されたスリバチ状の窪地であり、人知れず源流探索を続けるのが東京スリバチ学会なのだ。
皆川典久 〈みながわ のりひさ〉
東京スリバチ学会会長。地形を手掛かりに歩く専門家として、「タモリ倶楽部」や「ブラタモリ」に出演。
町の魅力を再発見する手法が評価され、2014年には東京スリバチ学会としてグッドデザイン賞を受賞した。
著書『凸凹を楽しむ東京「スリバチ」地形散歩』(洋泉社)が10月25日に新装刊。

