老後に備えるあんしんマネー学 第18回
さまざまな情報が飛び交うなか、老後資金に不安を抱えている人も多いのではないでしょうか。
お金を上手に管理して、老後を安心かつ心豊かに暮らすための、備えのマネー術を紹介します。
終活の最終章ともいえるお葬式への備え。
昔に比べて、家族葬を選択するご家庭が増えるなど、会葬者の人数が減っていることから、お葬式にかかる費用も減少傾向にあります。
とはいえ、一連の儀式には100万円を超える費用がかかるのが一般的です。
そこで今回は、お葬式にかかる費用をデータも交えてご紹介するほか、葬儀保険についてもご説明します。
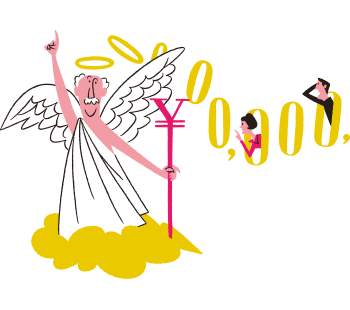
お葬式費用の平均額は
約120万円まずは、「第4回お葬式に関する全国調査」(株式会社鎌倉新書調べ)で、お葬式とその後にかかる費用(平均額)をご紹介します。
葬儀にかかる費用は、全国平均で119万1900円。2014年の第1回調査では、全国平均で130万3628円でしたので、減少傾向が確認できます。
葬儀の飲食にかかった費用は31万3800円。葬儀の返礼品費用は、33万7600円になっています。葬祭業者に会食を依頼せず、飲食を別に頼んだ場合などは、葬儀の当日、現金やクレジットカードなどで支払わなければならないケースもあります。葬儀を執り行う時点では、亡くなられた方の銀行口座は多くが凍結しているはずですので、遺族が立て替えて支払うことになります。
次は受けとる方の、香典代。香典の合計額は平均で71万1400円。71万円もの香典額は意外に多いと感じるかもしれませんが、最多価格帯は18・7%を占める10万円未満、ついで40万円以上60万円未満になっています。
次代の負担も考慮して決めたいお布施戒名代などによって、金額に幅が出るのはお布施ではないでしょうか。お布施の平均は23万6900円になっていますが、1万円以上10万円未満が27・6%と最多を占めています。
私の経験談になりますが、義父が亡くなり、戒名を付けていただく際、「最初の人に『院号』などを付けたら、この先同じお墓に眠る人には、同じランクの戒名を付けてもらいますが、よろしいでしょうか」と聞かれたことがありました。その時は「わかりました」と答えましたが、息子や孫たちにも同じ負担を課すわけで、戒名代は悩ましいなと感じました。
なお、火葬だけを行う直葬を利用する人もいます。葬儀を挙げてくれる親族がいない場合などに利用される方法で、一般的に10~40万円ほどかかります。
墓地の購入にかかった費用は、平均で135万円1200円。埋葬される場所は、一般的な墓地のほかに、納骨堂や樹木葬、海洋散骨などを利用する方法もあります。納骨堂は、建物の中に骨壺が並ぶ形で埋葬されます。最近は立体駐車場のように、カードをかざすと、骨壺が自動的に出てくるタイプの納骨堂も増えています。また、納骨堂で葬儀を行えるところもあります。
樹木葬は、霊園や寺内の樹木葬用に整地された場所に埋葬される方法です。里山に埋葬するイメージを持つ方もいますが、最近は都市部の寺でも、樹木葬のスペースを設けるところが増えています。樹木葬の場合の埋葬料はまちまちですが、十三回忌などの一定期間が過ぎると、合祀墓のほうに遺骨を移し、その後は共同で法要を執り行うのが一般的です。
海洋散骨は船を海に出し、水に溶けるようパウダー状に加工した遺骨を、参列者全員で海に撒く方法です。遺骨を撒いた場所は海図に記録し、一周忌法要の際、同じ場所に再び船を出して法要を行えます。過去に、東京湾と相模湾の海洋散骨の模擬法要に参加したことがあります。費用は会葬人数にもよりますが、12〜24名で20〜40万円が目安となります。
はたなか まさこ
ファイナンシャルプランナー。
新聞・雑誌・ウェブなどに多数の連載を持つほか、セミナー講師、講演を行う。
「高齢期のお金を考える会」「働けない子どものお金を考える会」などを主宰。
『ラクに楽しくお金を貯めている私の「貯金簿」』(ぱる出版)など著書多数。

