東西高低差を歩く関東編 第26回
地形に着目すれば、土地の歴史が見えてくる。
“高低差”の達人が紐解く、知られざる町のストーリー。
関東は皆川典久さん、関西は梅林秀行さんが交互にご案内します。
異人たちが驚いた
スリバチ? ~横浜・山手
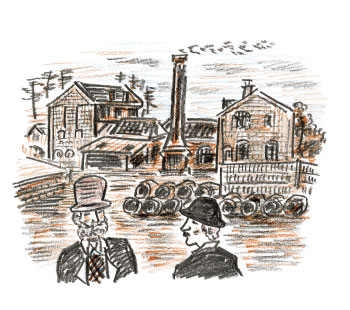
イラスト:牧野伊三夫
スリバチは大きな可能性を秘めている。
ここでいうスリバチとは、筆者が長年追い求めているスリバチ状の窪地のことであるが、その価値に気づいたのは、幕末に開港場横浜にやってきた異人さんたちだった。
本シリーズは土地の高低差が奏でる町の歴史や文化を、関西・関東と交互に紹介を続けている。東日本編では特に、スリバチ状の窪地を題材に東京エリアを中心に取り上げているが、今回は東京を離れ、横浜・山手の事例を紹介する。横浜のスリバチ地形は東京よりも高低差が大きく圧巻な風景が育まれている。そしてスリバチといえば谷底から湧き出る清水が特徴のひとつだが、その地形的ポテンシャルを活用して文明開化の時代には多くの産業が起立した。その立役者は地元の住民ではなく、海外からやってきた外国人たちであった。
まずは横浜の地名由来を「横濵村外六ヶ村之圖」からおさらいしておく。二つの台地に挟まれた釣鐘状の入江を塞ぐように、山手側の台地の麓から細長い微高地(砂嘴〈さし〉)が、海辺に横たわっている様子が描かれている。横浜の地名は、「海に向かって横に伸びた浜」からつけられたもので、砂嘴上にあったのが半農半漁の横浜村。1859年に開港場となった際に、地盤的にも安定したこの土地には外国人居留地が造られることとなった。そのために横浜村の住民が強制的に移住させられたのが山手の台地のふもと、当時元村と呼ばれた地。すなわち現在の元町のことである。外国人居留地の周囲には警備上、堀川がめぐらされ、堀を渡る橋には関所が置かれた。その内側が「関内」だ。それではいよいよ本題、外国人が発見したスリバチとは何処だったのか?そのひとつが山手の元町公園となっているスリバチ状の谷間。そのスリバチの可能性に気づいたのが、幕末に来日したフランス人実業家ジェラールだった。彼は湧き出る豊富な清水に目をつけ、開港場となった横浜港に出入りする船舶への給水事業を開始した。煉瓦造の地下貯水槽を整備し、一帯は水屋敷とも呼ばれた。残念ながら谷間にあった施設は関東大震災で被災し、その跡地を横浜市が買い取り整備したのが現在の元町公園である。ちなみに横浜の中心市街地では開港以来、井戸は塩分と濁りでほとんど飲用の役に立たなかったという。そこで水売業者が遠方から水を運搬していたが、増大する需要には応じきれず、近代式改良上水道が1887年に整備されるまでは深刻な水不足が続いていた。
そしてもうひとつが、ビール発祥の地となったスリバチ。その場所は現在、市立北方小学校の敷地となっているが、かつて北方村天沼と呼ばれた清水の湧く土地であった。1868年にアメリカからやってきたウィリアム・コープランドは、このスリバチで湧く清水を利用してビール製造に着手、醸造所はスプリング・バレー・ブルワリーと名付けられた。その後、経営不振に陥ったコープランドは醸造所を手放すこととなったが、跡地にジャパン・ブルワリーが設立され、天沼の谷でのビール製造は再開されることとなった。同社が製造するビールは「キリンビール」の銘柄で全国に販売され、1907年には麒麟麦芽酒造株式会社と社名を変えた。ビール工場はジェラールの水屋敷と同じく関東大震災で被災し、鶴見区生麦に移転して現在にいたっている。
身近にあるものの価値は意外と見過ごしやすい。別世界からやってきた人が、あるいは視点を変えることによって、お宝(スリバチ)の価値に気づくものなのかもしれない。本連載主旨、土地の高低差に着目する意味もその辺にあると考えている。
皆川典久 〈みながわ のりひさ〉
東京スリバチ学会会長。
地形を手掛かりに町を歩く専門家として『タモリ倶楽部』や『ブラタモリ』に出演。
著書に『東京スリバチ地形散歩』(宝島者)や『東京スリバチの達人/北編・南編』(昭文社)などがある。
都市を読み解くツールとして『東京23区凸凹地図』(昭文社)の制作にも関わった。

