東西高低差を歩く関東編 第30回
地形に着目すれば、土地の歴史が見えてくる。
“高低差”の達人が紐解く、知られざる町のストーリー。
関東は皆川典久さん、関西は梅林秀行さんが交互にご案内します。
~神楽坂~
高低差が伝える古城
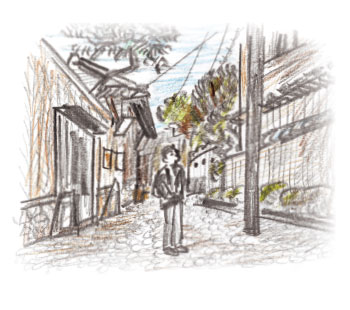
イラスト:牧野伊三夫
東京は坂の町である。1970年代にヒットしたフォークソング、グレープ(作詞・作曲はさだまさし)が唄った『無縁坂』や、1925年に発表された江戸川乱歩の探偵小説『D坂の殺人事件』の舞台となった「団子坂」など、全国的に知られている名所的坂道は多い。その中でも知名度の高い坂道に挙げられるのが「神楽坂」であろう。
JR飯田橋駅西口から外堀通り越しに北を眺めると、人通りの多い直線状の坂道が目に入る。街路樹に包まれた、その緩やかな坂道こそが神楽坂。和菓子屋や雑貨店などの老舗に加え、個性的な店舗が坂道に軒を連ねる。メインストリートである神楽坂から逸れても、石畳の路地や石段が迷路状に続き、隠れ家のような店が点在するブラブラ歩きも楽しいエリアだ。
JR飯田橋駅前にあったのが江戸城三十六見附のひとつ牛込見附。枡形だった石垣の一部が残され、直下には外濠が豊かな水を湛えている。かつてはこの辺りまで船での遡上〈そじょう〉が可能で、神楽河岸と呼ばれる荷揚げ場が存在していた。河岸は残念ながら埋め立てられて、再開発ビルに置き換えられている。
神楽坂は鎌倉街道の道筋のひとつで、坂上にある善國寺の門前として江戸時代から賑わった。善國寺のご本尊である毘沙門天像は民衆からも厚い信仰を受けていた。門前には岡場所があったとされ、明治時代に入ってからは花柳界となって盛況する。明治20年前後からは、毘沙門の縁日に夜店が出されるようになり、大正の頃までは山手繁華街の中心地でもあった。
神楽坂の名の由来は「どこからか神楽が聞こえてくる坂道」のようだが、神楽が奏された場所には諸説あり定かでない。牛込御門、若宮八幡、筑土八幡、市谷亀岡八幡などがその候補地。神社は台地の突端に立地することが多いのだが、神楽坂周辺に神社が多いということは、それだけ複雑な地形を有している証拠。凸凹地形図からも岬状の土地に祀られた神社と、台地を掘り割る谷筋が多いのが分かる。
このような複雑な凸凹地形を利用して立地したのが中世の古城・牛込城。現在の光照寺あたりに居館地があったとされるが詳細は不明。牛込氏とは群馬県大胡〈おおご〉城(赤城山南麓)から移り住んだ大胡氏が、土地の名「牛込」を姓に改めたもので、神楽坂近くに赤城神社があるのは大胡氏が故郷の神社分霊を牛込の鎮守として祀ったから。ちなみに「牛込」という名は、牧場が往古あったからと思われる。馬込・駒込などと同様に、高燥〈こうそう〉の台地につけられる特徴的な地名でもある。
戦国時代の天文6(1537)年前後の頃、小田原北条氏がこの地に招いた大胡氏(牛込氏)は、家臣として赤坂・桜田・日比谷あたりまで領していたが、北条氏滅亡のあとは徳川氏の家来となり牛込城は廃止された。そして正保2(1645)年に、神田にあった光照寺がこの地に移転してきたのだった。
もう一度凸凹地形図を眺めてみると、城のあったとされる土地が、いくつもの谷筋に囲まれていることに気づく。現在の地名は「袋町」、谷に囲まれた袋状の土地柄なのだ。城の北側にある弁天坂(大久保通り)の谷筋が北方を守る堀に相当する。城域南側にも小さな谷があり、地元では「空堀通り」と呼ばれ、静かな商店街となっている。この谷は自然地形か人為的なものかは定かでない。けれども牛込城の堀の遺構だと思われ、賑わう神楽坂の路地裏で静かに歴史を語りかけている。古城の場合、建築物などは失われることが多いのだが、空堀や土塁など土地の高低差は意外に残されている場合が多い。高低差にまつわる物語は意外な場所に潜んでいるのだ。
皆川典久 〈みながわ のりひさ〉
東京スリバチ学会会長。
地形を手掛かりに町を歩く専門家として『タモリ倶楽部』や『ブラタモリ』に出演。
著書に『東京スリバチ地形散歩』(宝島者)や『東京スリバチの達人/北編・南編』(昭文社)などがある。
都市を読み解くツールとして『東京23区凸凹地図』(昭文社)の制作にも関わった。

