東西高低差を歩く関東編 第34回
地形に着目すれば、土地の歴史が見えてくる。
“高低差”の達人が紐解く、知られざる町のストーリー。
関東は皆川典久さん、関西は梅林秀行さんが交互にご案内します。
鎌倉(後編)
~防災都市のプロトタイプ
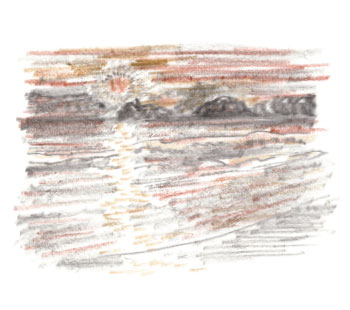
イラスト:牧野伊三夫
前回は鎌倉の立地的特色として、海と丘陵に囲まれた「要害の地」であること、地形的特色としては「谷戸〈やと〉」を活かした宗教都市の一面を紹介した。今回は臨海都市としての宿命と土地の高低差に着目した都市づくりの構想について思いをめぐらせたい。
鎌倉の中心市街地は東西約2.5㎞・南北約1.8㎞のコンパクトシティ。源頼朝の入府以降、狭隘〈きょうあい〉な地ゆえ丘陵の裾部を切り拓いては低地を埋め、より多くの平坦地を造成するという都市改造が行われてきた。鎌倉地方では、山裾を切り拓いた際の泥岩塊を「土丹」と呼び、土丹を使用した整地を「地業」と呼んでいるが、現在の市街地が比較的平坦なのは、この地業と呼ばれる大規模な嵩上げ工事が、平安時代の末期から近代を通じ、繰り返し行われた結果だ。発掘調査によれば、鎌倉駅付近では2m、鶴岡八幡宮でも約1.5mもの盛土が成されたことが分かっており、武士が闊歩した中世の鎌倉の地盤面は現在自分たちが踏みしめている客土層の下に眠っているわけだ。
地業が行われたのは、土地が狭隘だったからだけではない。『鎌倉市史考古編』によれば、縄文時代は現在の等高線で10mあたりが海岸線だったらしく、鎌倉湾が現在の若宮大路を中心とした市街地の大半に入り込み、扇ヶ谷あたりまで水辺が迫っていた。現在に近い海岸線と地形が形成されたのは、約2000年前の弥生時代の頃とされ、丘陵からは多くの河川が流れ込み、現在の海岸線より内側に幾筋かの砂丘列(浜堤)があった。今の市街地の大半は、丘陵地と浜堤に挟まれた後背湿地(ラグーン)に沖積層〈ちゅうせきそう〉が堆積した土地であり、多くは沼地や湿地があったと思われる。したがって、この地を繰り返し襲ったであろう自然災害(洪水や津波)から都市を守り、衛生的にも良好な宅地開発を進めるためには嵩上げ工事が必要だったに違いない。
古代東海道が通っていたのは海岸線と平行な微高地(浜堤)で、その標高は鶴岡八幡宮の門前と同じで海抜10m程度の高さを持っている。若宮大路の一ノ鳥居はこの微高地上にあり、若宮大路が鶴岡八幡宮に向かって緩やかに下っているのはそのためだ。
鶴岡八幡宮の参道として北条政子の安産祈願に際し整備された若宮大路の構造を詳しくみておきたい。
若宮大路の中央に二条の土堤を築き、その基部に葛石を敷いたことから「段葛〈だんかずら〉」と呼ばれる。大路の幅は約33m、二ノ鳥居から三ノ鳥居までの間には、幅約3m、深さ約1.5mの木組みの側溝があったことが発掘調査で分かった。段葛は鶴岡八幡宮から二ノ鳥居までが現存するが、その海側すなわち一ノ鳥居との間が失われているのは室町時代の洪水と明治時代の官有地編入によるものらしい。浜堤上の一ノ鳥居から始まるかつての段葛は元々、後背湿地を貫き山際に建立された鶴岡八幡宮へと一直線に導いていたわけだ。
参道としての段葛の構造は、湿地帯対策と見るのが妥当であろうが、もう一つの設計思想があったのではないかと地形マニアとして想像している。
それは鶴岡八幡宮を聖域と位置付けるだけでなく、「安全」な標高を持った「津波避難施設」と用意したのではないかというものだ。誰もが知り町のセンターを貫く道、それを辿れば高台へと導かれる都市構造は信仰的な象徴性に加え、防災的な視座を教示してくれているように思えてならない。
東国で誕生した武士の都には、津波や高潮・洪水など自然の驚異から住民を守るシステムが内在していたとみなすのは妄想が過ぎるだろうか。「鎌倉城」とは、攻め入る敵に対して鉄壁の防御の構えを持つのみならず、時には牙をむく自然災害に対しても「備え」を持った防災都市のプロトタイプだったのかもしれない。
皆川典久 〈みながわ のりひさ〉
東京スリバチ学会会長。
地形を手掛かりに町の歴史を解き明かす専門家として『タモリ倶楽部』や『ブラタモリ』に出演。
著書に『東京スリバチ地形散歩』(宝島社)や『東京スリバチの達人/分水嶺北編・南編』(昭文社)などがある。
2022年にはイースト新書より『東京スリバチ街歩き』を刊行。
シリーズ化が始まった昭文社の『凸凹地図帳』と『スリバチの達人』の総合監修を務める。

