東西高低差を歩く関西編 第13回
地形に着目すれば、町の知られざるすがたや物語が見えてくる。
第13回は、京都・東本願寺と京都駅。
京都のランドマークが体現する、この都市のドラマとは。
東本願寺と京都駅
「伽藍再建」と「道路拡幅」
二つの近代化
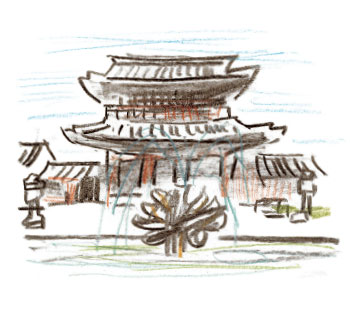
イラスト:牧野伊三夫
「駅」はまちの性格を特徴づける。そして「駅前」には、各都市ならではの表情が生まれているものだ。
京都にとって、駅とはまず京都駅のことだろう。京都駅を出て、市街地中心部に向けて北上するや否や、すぐに視界に飛び込むものは東本願寺の偉容である。世界最大級の木造建築「御影堂〈ごえいどう〉」をはじめ、東本願寺は京都市内きってのランドマークといえる。
ここで京都駅から東本願寺までの道のりを、少しだけ戻りたい。東本願寺から京都駅に向かって約70m南へ向かった地点に、高さ約1mの段差が東西に連なっている。これは東本願寺が領主となって開発した、独自の市街地「寺内町〈じないまち〉」の南限にあたる地点だ。戦国時代の一向一揆を経て、近世社会の内部に組み込まれた本願寺教団は、京都市街地の南部開発を新たに期待された。東本願寺と西本願寺の両寺が、二条城や京都御所から大きく離れた京都の南部に並んで立地しているのは偶然ではない。
このうち京都市街地の南東部開発を担って創立された東本願寺は、境内周囲の低湿地を盛土造成しながら市街地を建設していった。先ほど紹介した段差は、東本願寺が推進した近世ニュータウン事業の南限ラインにあたるものだったのだ。
新たな市街地は盛土を伴って生まれる。世界共通の歴史法則(?)が、このような段差を生んでいった。
一方で近世社会と同様、あるいはそれ以上のインパクトを放った歴史的出来事は、「近代」の成立である。近代といえば、駅建設とセットの鉄道事業がその申し子といえるだろう。明治10年(1877)開業の京都駅も、近代京都の成立と発展の象徴的存在だった。
ここで京都駅の地理条件を考えてみる。駅を含めた鉄道建設は一般的に広大な敷地を必要とするため、用地買収などのコストを考えると旧市街地の内部には建設しがたい。したがって駅は旧市街地の内側ではない、かといって離れすぎない場所に立地することになった。京都駅もその例に漏れず、京都の旧市街地外縁部(東塩小路村)に建設された。
そして旧市街地外縁に立地する鉄道駅は、駅と旧市街地を結ぶ「駅前道路」の建設を新たに必要とした。京都の場合、京都駅と京都御所を結ぶ「烏丸〈からすま〉通」が駅前道路に指定されて、京都市の都市整備事業のなかで、近世には道幅10mに満たない道路が、路面電車の開通を含んだ道幅30mの近代道路として大きく生まれ変わった。
そこに待ったをかけたのが、東本願寺である。京都市の都市整備と並行して、東本願寺も「伽藍再建」という独自の近代化を進めていたのだ。幕末動乱(禁門の変)のなかで伽藍を全焼した東本願寺にとって、近代化とはそのまま伽藍の再建を意味していた。数多くの門徒から物心両面の支援を受けて、東本願寺の伽藍再建は明治44年(1911)にようやく完成を迎えようとする。
しかしまさに時を同じくして、駅前道路として拡幅された烏丸通の整備事業が、東本願寺の門前すぐ目の前まで進もうとしていた。東本願寺としては、悲願の伽藍再建を盛大に祝おうとしたそのとき、目の前を巨大道路が突き破るようなものである。それは新伽藍の偉容を損なうものだろうし、なにより伽藍再建を祝って全国から集う門徒たちの安全が懸念された。
東本願寺は烏丸通の整備事業変更を求めて、京都市に要望書を送った。境内門前を通過する、烏丸通の「迂回」を求めたのである。その際、道路計画変更で発生する費用負担にも応じている。結果、当時の京都市当局は東本願寺の要望を受け入れて、境内門前で烏丸通を大きく迂回させることを決定した。
もちろん計画変更がすんなり決まったとは思えず、歴史の表舞台には出ないドラマがそこにはあっただろう。しかし道路拡幅(京都市)と伽藍再建(東本願寺)という、二つの異なる主体からの近代化は、摩擦を生みながら、現在の東本願寺門前に展開する烏丸通の大カーブを誕生させたのである。京都の市街地拡大の主役だった東本願寺と京都駅。この両者が生んだドラマを、京都駅前に残る段差と道路カーブから見て取りたい。
梅林秀行 〈うめばやし ひでゆき〉
京都高低差崖会崖長。高低差をはじめ、まちなみや人びとの集合離散など、さまざまな視点からランドスケープを読み解く。「まちが居場所に」をモットーに、歩いていきたいと考えている。NHKのテレビ番組「ブラタモリ」では節目の回をはじめ、関西を舞台にした回に多く出演。著書に『京都の凸凹を歩く』など。

